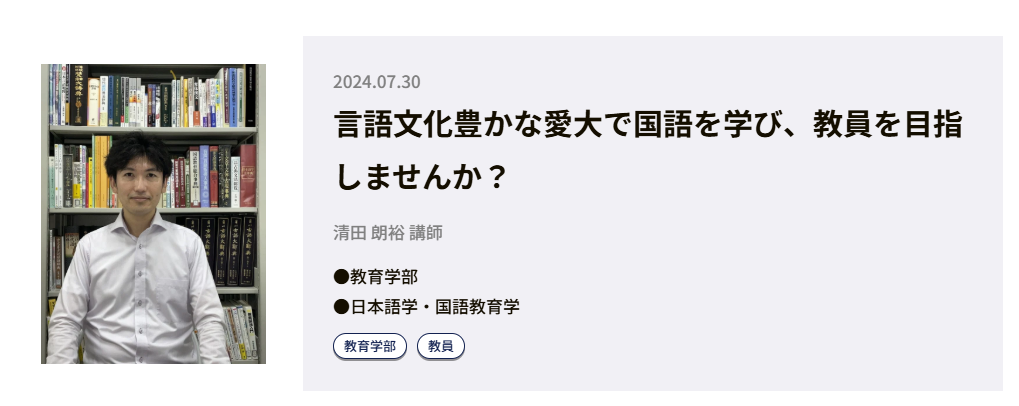2025年2月2日発行の朝日中高生新聞の特集には、「読む」が減った高校国語を危ぶむ専門家の清田朗裕(きよたあきひろ)さんへのインタビュー記事がありました。
(このページはプロモーションが含まれています)
大丈夫?「読む」が減った高校国語の記事概要
高校の国語の授業では、文学作品に触れる機会が減っているそうです。
2022年の学習指導要領が変わった影響らしいのですが、高校国語の定番である文学作品を読みこむ時間が今の高校生の授業数では圧倒的に足りないようです。
『現代の国語』で取り扱う実用的な文章とは、簡単に言うと取扱説明書。取扱説明書は、いろんな読み方ができたら困ってしまいますよね。だから、そういったものを正確に読み取る力は、たしかに必要です。
朝日中高生新聞(2025/2/2)特集記事 清田さんの言葉から
清田さんは、これらのことはAI(人工知能)が担ってくれることかもしれないと言います。
しかし、古くから親しまれてきた高校国語の定番文学作品を読むことについては、
一人ひとり違った読み方ができ、同じ人でも人生経験を積むことによって、以前とは異なる読み方ができます
朝日中高生新聞(2025/2/2)特集記事 清田さんの言葉から
「取扱説明書」ということばに少し驚きましたが、他にも、「書かれていないこと」に対してどう向き合うかや、「多様な読み方は生きる土台になる」ということも書かれていて、とても良い記事でした。
購読の申し込み
朝日中高生新聞【公式】から申し込み👇
※リンク先ページの右下「朝日中高生新聞」ボタン
から申込してください

(探求・小論文・受験・面接向き)
読売中高生新聞【公式】から申し込み👇
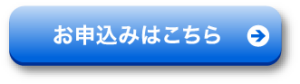
(雑誌感覚で読みたい人向き)
高校国語の定番文学作品とは
高校国語の定番文学作品とは、親世代にはなつかしい、必ず高校で読まされた文学作品でした。
◆夏目漱石「こころ」
◆中島敦「山月記」
◆森鴎外「舞姫」
その他には、梶井基次郎の「檸檬」や、芥川龍之介の「羅生門」なども挙げられるそうです。
専門家の清田朗裕さんとは
こちらの記事でインタビューに答えている専門家は、清田朗裕(きよたあきひろ)さんでした。
現在、愛媛大学教育学部で講師をされており、「未来の愛大生へ」の中で「国語(科)はすべての教科の基礎・基本だ」ということを語っています。
引用:愛媛大学ホームページ https://www.ehime-u.ac.jp/data_voice/kiyota-akihiro/
その他の特集記事の内容
特集記事は、「文学」について高校生の今、考えるという内容でした。
その他の記事は以下の通りです。
- 国の「文系」に対する方針について
- 大学受験の変化は?
- 文系・理系の就職率について
- 高橋源一郎さんに聞く、文学とはなんなのか
- 大学で文学を学んでいる学生2人へのインタビュー
かなりまじめな記事ではありますが、中高生に読んでほしい内容がたくさんありました。
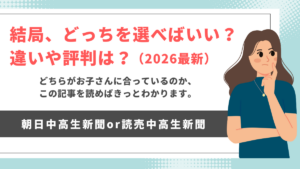
購読の申し込み
朝日中高生新聞【公式】から申し込み👇
※リンク先ページの右下「朝日中高生新聞」ボタン
から申込してください

(探求・小論文・受験・面接向き)
読売中高生新聞【公式】から申し込み👇
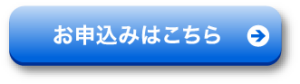
(雑誌感覚で読みたい人向き)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44844c60.3f267b1f.44844c61.7916fdd9/?me_id=1213310&item_id=11295032&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0137%2F9784101010137.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44844c60.3f267b1f.44844c61.7916fdd9/?me_id=1213310&item_id=18274658&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4128%2F9784480434128_1_53.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44844c60.3f267b1f.44844c61.7916fdd9/?me_id=1213310&item_id=16399529&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8430%2F9784041008430_1_2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)